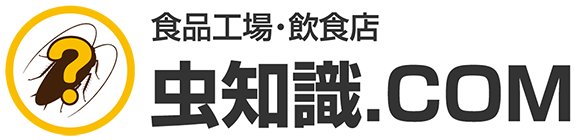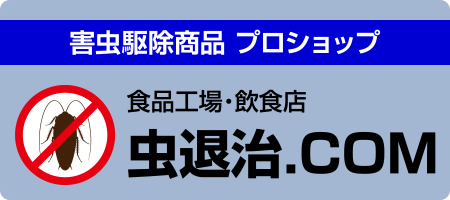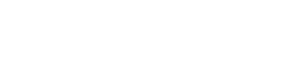ネズミの種類や生態を知る
日本の家屋で主に見られるのは、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種類です。
駆除方法を調べているのであれば、まずは、ねずみを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。種類やその特徴を知ることで、対策の際に、より適切な方法を選択できるようになります。
ねずみの駆除方法と対策を知る
ねずみはビルや家屋といった私たちの身近なところに住みつき、様々な被害をもたらします。
建材や電気や電話の配線などを齧り、電気設備を故障や火災を起こす場合があります。
また、ダニの発生の原因となったり、病原体・寄生虫を媒介し、食中毒の原因になるなど、衛生面での被害もあり、侵入を防ぐ、駆除するなどの対策することが大切です。
プロがすすめる駆除アイテムを知る
ねずみの侵入の侵入を防ぐ、捕獲する、殺鼠剤を用いて駆除するなど、目的に合わせた駆除アイテムを害虫のプロが紹介します。