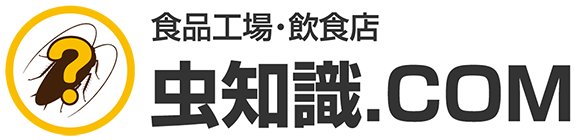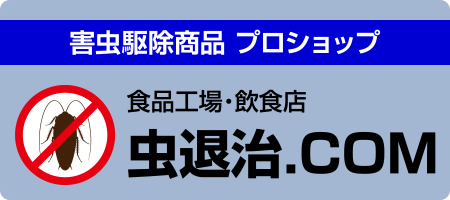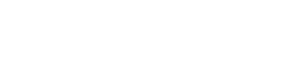カメムシの生態・種類
 カメムシ類の多くは危険を感じると悪臭のある分泌物を出すことで知られています。 この分泌物は外敵の撃退するためや、仲間へ警戒を知らせる一種のフェロモンとして作用していると考えられています。
カメムシ類の多くは危険を感じると悪臭のある分泌物を出すことで知られています。 この分泌物は外敵の撃退するためや、仲間へ警戒を知らせる一種のフェロモンとして作用していると考えられています。
カメムシは、卵→幼虫→成虫へと3段階に変化します。
成虫は、幼虫の餌となるもの(例:植物)に卵を産み付けます。
孵化した幼虫は、成虫と似た姿をしていますが、羽はまだ生えていないため飛ぶことはできません。
カメムシ類は幼虫・成虫ともに針のような細いストロー状の口を持ち、葉や茎、果実など餌となる植物に刺して汁を吸います。(種類によっては、他の昆虫を餌にする肉食性のカメムシもいます。)
- ■カメムシによる被害
- カメムシ類の一部の種は、9月~11月頃の秋になると越冬のために隙間や割れ目、日当たりの良い場所を求めて飛んできます。その際、家屋の羽目板の隙間や屋根裏、外壁などに集団で集まります。
また、家屋内にも侵入、悪臭を放つため問題となります。カメムシ類は越冬から覚めて飛び出してくる3月~5月頃の春先にも再び問題となります。
カメムシ類の害として悪臭のほか、サシガメの仲間によって刺される被害がありますが、日本においては特に問題となる種は存在しません。
マルカメムシ -Megacopta punctatissimum-

| 分類 : | マルカメムシ科 | Plataspidae |
|---|---|---|
| マルカメムシ属 | Megacopta | |
| マルカメムシ | Megacopta punctatissimum |
マルカメムシ科の一種。体長は5mm前後で、暗褐色光沢のある暗褐色をしています。北海道を除く日本各地に分布し、成虫はヤマフジ、クズ、ハギなどのマメ科植物に寄生します。
寄生植物の一つ「クズ」は、高速道路の土手や河川の堤防、鉄道敷地、空き地などで生い茂っているツル草状の植物です。
この植物にマルカメムシが大発生するため、本種は特に都市近郊で問題となりやすいカメムシです。
成虫で越冬し、翌年の春、マメ科植物の葉や茎に卵を産み付けます。成虫は7月頃から見られるようになり、10月~11月になると越冬場所を求めて多数飛来・侵入し、問題となります。
クサギカメムシ -Halyomorpha halys-

| 分類 : | カメムシ科 | Pentatomidae |
|---|---|---|
| クサギカメムシ属 | Halyomorpha | |
| クサギカメムシ | Halyomorpha halys |
カメムシ科の一種。 体長は14~18mm、暗褐色で黄褐色の不規則な斑模様があります。日本では本州、四国、九州、沖縄に分布し、中部・北部では主に本種が問題となります。
モモ、ミカン、クサギなど多くの果樹の上で見られ、果実の汁を吸います。
夏から初秋に新成虫が現れますが、暖地では年2回成虫が発生します。秋は越冬のため家屋に大量に飛来、侵入し、悪臭を放ち問題となります。
都市近郊よりは山地周辺にある家屋で問題となりやすい。
スコットカメムシ -Menida scotti-

| 分類 : | カメムシ科 | Pentatomidae |
|---|---|---|
| Menida属 | Menida | |
| クサギカメムシ | Menida scotti |
カメムシ科の一種。体長は9~11mm、暗褐色で銅色の光沢をもつ。羽の先が腹部より長く突き出ている。北海道から本州にかけて分布し、東北や北海道では主に本種が問題となります。越冬時に家屋に大量飛来し、多い時には何万匹という大群が一軒の家に集まることもあります。
クサギカメムシ同様、山地に生息し、シナノキ、ヤマハンノキ、ミズナラなどの植物の汁を吸う。
アオクサカメムシ -Nezara antennata-

| 分類 : | カメムシ科 | Pentatomidae |
|---|---|---|
| カメムシ亜科 | Pentatominae | |
| Nezara属 | Nezara | |
| アオクサカメムシ | Nezara antennata |
カメムシ科の一種。体長は12~16mmで、光沢のない緑色をし、色彩変異も多い。背中に3つの星状の黄斑があります。日本全土に分布し、各種の草・樹木・野菜・果樹などを好んで吸汁します。灯火に飛来するため、不快害虫として問題となる。
目的や発生場所に合った対処方法を知る。
カメムシの駆除方法と対策成分や目的から駆除剤を選ぶ。
プロがすすめる駆除アイテム